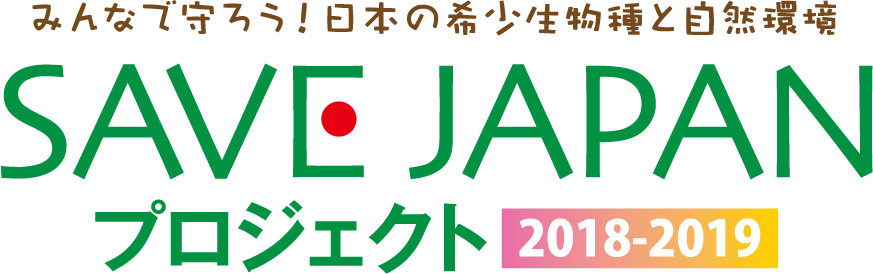ツキノワグマと同じ時代に生きる幸せ~人とクマの境界づくり
2019年06月16日(日)実施

レポート
当日のスケジュール
2班に分かれて出発し、途中合流をした。
バスA班(出雲西高等学校)
8:30 出発
9:00 到着。事前打ち合わせ、発表のリハーサル
バスB班(一般参加者)
8:00 島根県庁郵便局前出発
8:40 ふるさと森林公園学習展示館前出発
9:50 スサノオホール到着
バスA班、バスB班共通
10:00 講義「ツキノワグマと同じ時代を生きる幸せ」
出雲西高等学校インターアクトクラブによる、「環境活動発表」
11:00 スサノオホール出発
それぞれの移動バスの車内で、「里山とツキノワグマについて」お話
11:30 吉野林地で現地見学
12:10 吉野林地出発
12:40 スサノオホールにて、昼食交流会
13:20 記念撮影、アンケート記入
自家用車の方は、ここで解散
バスA班(出雲西高等学校)
13:40 スサノオホールを出発
14:00 出雲西高等学校到着
バスB班(一般参加者)
13:30 スサノオホール出発
14:20 ふるさと森林公園学習展示館前で解散
15:00 島根県庁郵便局前で解散
バスA班(出雲西高等学校)
8:30 出発
9:00 到着。事前打ち合わせ、発表のリハーサル
バスB班(一般参加者)
8:00 島根県庁郵便局前出発
8:40 ふるさと森林公園学習展示館前出発
9:50 スサノオホール到着
バスA班、バスB班共通
10:00 講義「ツキノワグマと同じ時代を生きる幸せ」
出雲西高等学校インターアクトクラブによる、「環境活動発表」
11:00 スサノオホール出発
それぞれの移動バスの車内で、「里山とツキノワグマについて」お話
11:30 吉野林地で現地見学
12:10 吉野林地出発
12:40 スサノオホールにて、昼食交流会
13:20 記念撮影、アンケート記入
自家用車の方は、ここで解散
バスA班(出雲西高等学校)
13:40 スサノオホールを出発
14:00 出雲西高等学校到着
バスB班(一般参加者)
13:30 スサノオホール出発
14:20 ふるさと森林公園学習展示館前で解散
15:00 島根県庁郵便局前で解散
実施内容
講義
・ツキノワグマの生態について正しく知る。
・ツキノワグマと人との共存を考えるなどを取り上げました。
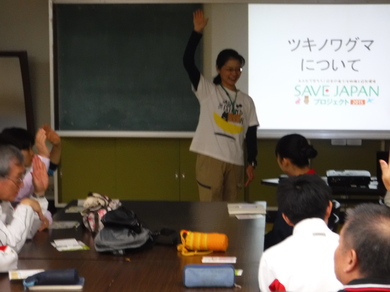
高校生による環境に関する活動報告
・サケの稚魚の孵化から飼育、放流までの一連の活動
・フィールドの竹林整備や植樹について、報告を行いました。
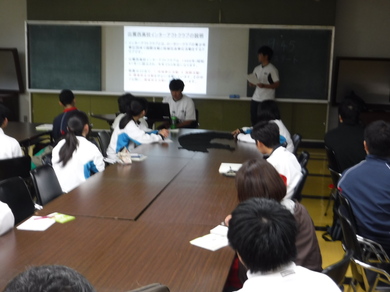
・イベント当日は、晴れていれば、棚田を整備作業する予定でした。当日は雨のため、フィールドの見学に切り替えて開催しました。
・続いて、昨年度植樹した場所を見学しました(フィールドの草刈は、事前にもりふれ倶楽部はじめ地域の方が作業)。人が手を入れ境界線を作ることで、実際に野生動物の被害が減ってきたことを聞くことができました。
・昨年度、出雲西高等学校生が山桜を植樹したフィールドを見学しました。当日は植樹を行った生徒が同行しており、山桜が枯れずに根付いている姿を見て、喜ぶ姿が見られました。
・昨年度、SAVE JAPANプロジェクトで整備したフィールドを見学しました。参加者に向けて、継続して整備し続けていることをお話しました。

このイベントで得られたこと
・ツキノワグマは、中国地方の生態系のピラミッドの最上位に位置づけられています。しかし、人と接触することで駆除されるという不幸な事件が増えています。背景の1つに里山の維持管理ができなくなったことが挙げられます。そのため、本日のイベントを通して、里山と奥山の境界づくりが大切である事を実感してもらえたと思われます。環境保全を考えるきっかけになり、活動を継続していきたいという声を多く得ることができました。
・出雲市西高等学校の取組について、報告する機会を得ることができた。これまでの成果を発表する機会を通して、高校生にとっては自信につながったと思われます。
参加者の声
- ツキノワグマの事や植えた木の状況などがよく分かった。まだまだ知るべきである。 (女性/学生)
- 自分で植えた木を見て感動しました。(男性/学生)
- 山の管理の理想的な方法や、ツキノワグマの大きさや足の速さなど分かりやすく教えてもらえました。(女性/50代)
- 環境問題や絶滅危惧種について普段考えたり知る機会がないが、専門家の話が聞けて理解が深まった。(男性/50代)
- 生憎の雨であったが、NPO法人もりふれ倶楽部の皆さんの熱意でとても良い研修になりました。これからも積極的に参加していきたいと思います(男性/60代)
イベント実施結果
- 参加者数
- 49名(高校生以上46名、子ども3名)
- アンケート回答数
- 40
- 参加者満足度
- 75.7%
- 実施してよかった点
- ・ツキノワグマをテーマに取り上げることで、参加者は、里山とツキノワグマについて理解が深まったと思われました。参加者にとっては、島根県の里山の現状や環境保全に関わっている人の活動を知り、環境問題を考えるきっかけとなったのではないでしょうか。実際に参加者から、今後、環境保全に積極的に関わりたいと思うと聞くことができました。
・参加者と高校生、そしてスタッフが昼食を共にすることにより、積極的に意見交換の場ができました。和気あいあいとした雰囲気で終えることができて、良かったと感じています。
・雨の中ではありましたが、参加者に自然の大切さを伝えることができて良かったと思います。 - 実施して苦労した点
- 雨天だったため、雨プログラムに切り替えて開催しました。参加者満足を維持するために、現地での研修時間を短くし、移動するバスの中で、ツキノワグマや環境問題の話題をし、イベントの補足をしました。
- 特に寄付が活きたと感じた点
- バスを利用できたことが大きいです。雨天ではありましたが、フィールドまで団体行で移動することができて、事故。怪我無く運営することができました。
メディア掲載
2019年6月18日(火)島根中央新報 地域版「出雲」
人とクマ 共存を目指す
- 主催・共催
- 主催:特定非営利活動法人自然とオオムラサキに親しむ会
共催:公益社団法人日本環境教育フォーラム - 協力・後援等
- 協力:認定特定非営利活動法人日本NPOセンター
- 協賛
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社