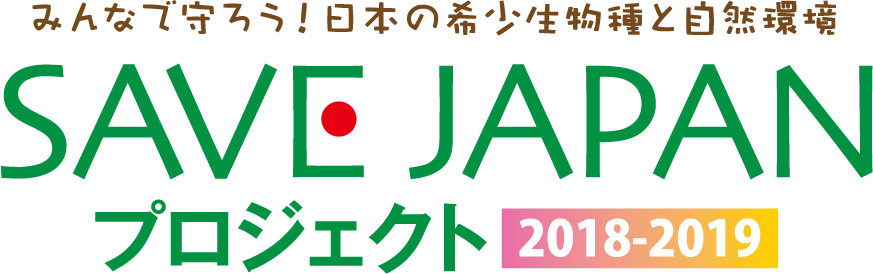サシバの里にドングリの木を植えよう!
2018年12月08日(土)実施

レポート
 「サシバというタカは里山の生態系の頂点。その生息密度は栃木県の市貝町付近が全国で一番」と遠藤さん。
「サシバというタカは里山の生態系の頂点。その生息密度は栃木県の市貝町付近が全国で一番」と遠藤さん。「でも、里山はそこに住む人が利用して維持してきたもので、ここ市貝はクヌギの雑木林を伐採し炭焼きをしてきた」とのこと。
でもこの40年は、薪、炭は、プロパンガス・電気になり、家庭で利用しなくなった。すると、里山ではなく〝奥山〟〝深山〟になってしまい、田んぼと山が混在する平地林に、カエル・ヘビ・虫などの生き物がいなくなり、結果、里山の生態系の頂点のサシバも住めなくなるといいます。
「サシバを守ることが雑木林を守る。さらに、そこに暮らす人の暮らしも守る」と言います。SDGsの実践として植林していたんだな、と思いました。

当日のスケジュール
9:30/道の駅「サシバの里」集合
9:30-9:40/植林会場移動
9:40-10:00/主催者挨拶・説明
10:00-11:30/植林
11:40/移動
11:50-12:40/昼食
12:40-13:00/まとめ

9:30-9:40/植林会場移動
9:40-10:00/主催者挨拶・説明
10:00-11:30/植林
11:40/移動
11:50-12:40/昼食
12:40-13:00/まとめ

実施内容
 薄曇りのち晴れの天気のなか、植林はじめての人ばかり20人ほどが集まって開催されました。300m×200mの斜面が現場。雑木林を伐採した跡地に、冬枯れのヤマにクヌギの苗木を植えるのが今日のミッションでした。
薄曇りのち晴れの天気のなか、植林はじめての人ばかり20人ほどが集まって開催されました。300m×200mの斜面が現場。雑木林を伐採した跡地に、冬枯れのヤマにクヌギの苗木を植えるのが今日のミッションでした。まず、クヌギの植林と里山の生物の関係について話を聞いたあと、ヤマの斜面に専用の穴掘り機(エンジン付きのドリル)で30cmの穴をほり、そこに1人10本(合計200本)を植えました。実生から4年の苗木は高さ80㎝位。植えた後、ビニールのリボンを目印に縛ってできあがり。夏の下草刈りの時に苗木を間違って刈らないための目印だとのこと。「ただ植えればいい」だけじゃないんだな、と思いました。
穴は掘ってあったので1時間で終了しまいしたが、前日に植えていた600本にも目印をしばったのでさらに30分かかりました。「人手が多いので助かった」と片岡林業の片岡さん。縛るだけで一人でやったら半日はかかるだろうな、と思いました。
このイベントで得られたこと

SDGsの実践として植林していたんだな、と思いました。
クヌギの雑木林は植えて7年目で伐採し、茶道用の菊炭にして全国に販売します。「太いクヌギでは菊炭にならない」と片岡さん。7年目に定期的伐ると伐り株からまた生えてくる。こうやって里山を維持するんだなと知りました。この地域の持続可能な社会(SDGs)はこれだったんだと勉強になりました。
また、生物と生活が共存するのが里山だとわかりました。夏に来た時にはクワガタ・タガメ・ミズカマキリなどがたくさんいて子どもたちが大喜びでしたが、冬には枯野で何も利用できない山に変貌。しかし、片岡さんは「これからが炭焼きの本番」と言います。「12月から木を伐って、炭を100窯焼く」とのこと。1回2トンの木を入れて、750kgの炭ができる?とか。(数字はうろ覚えですが…)
里山の暮らしは食と燃料(現金収入)が季節ごとに入れ替わるのだと知りました。子どもたちは面白くないですが、お金のことは大人は面白かったかもしれません。
自然の長期サイクル(遷移)をうまく利用した先人のSDGsに感服しました。
参加者の声
- 活動の意味を翌説明してくれたことで、身の回りの環境の保全により関心が高まった。
- 木が育つ将来を想像しながらとても楽しく植えられた。知識も増え面白かった。
- 初めて木を植えたので勉強になりました。里山と生き物の関係をまなべました。
- 予想以上に楽しかった。進路の参考になった。
- 協賛としての参加でしたが、熱心に皆さまが活動され、楽しく活動できました。
イベント実施結果
- アンケート回答数
- 15人
- 参加者満足度
- 93%
- 実施してよかった点
- ①SDGsという切り口を直接示せる企画だった。過去の暮らしを「今、これから」にも生かせるようにリニューアルできるメニューとなった。
②自然保護系でない普通の人たちが多数参加できる企画であった。 - 実施して苦労した点
- 参加者あつめ。生物がいない時期なので、子ども連れに期待できす、自然保護系の団体以外の参加者の確保が難しい。
- 特に寄付が活きたと感じた点
- ・地元林業関係者と連携したことで、NPOだけではできない広がり・活動の深まりが可能になった。
・現実的に、持続可能な「里山資本主義」への道筋が見えてきた。(菊炭は通常の炭の価格の数倍であり、それで若者が田舎で仕事になり、食べていけるものである)
メディア掲載
2018/11/21・下野新聞「サシバの森にクヌギを植えよう」
2018/12/9・下野新聞「サシバと菊炭に思いはせ クヌギ苗200本植樹」
2018/12/9・下野新聞「サシバと菊炭に思いはせ クヌギ苗200本植樹」
- 主催・共催
- NPO法人 オオタカ保護基金
認定NPO法人 とちぎボランティアネットワーク
片岡林業 - 協力・後援等
- 日本NPOセンター
損保ジャパン日本興亜 - 協賛
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社