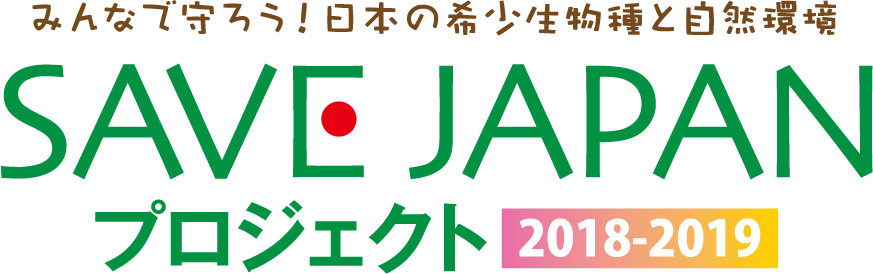里山を整備し希少生物種が生息するビオトープを次世代へ引き継ぐこと
活動内容
実施団体の会員と地域住民によるボランティア活動により、里山の整備、水辺環境(ビオトープ)づくり、大清水沢周辺に生息する貴重な動植物の保護活動などを通して、森林と水との関係、里山と動植物の関係、森林と林業の関係、人と自然との共生等について考える参加型森づくり活動を行います。
具体的には、2019年5月から、遊学の森明採り沢周辺と休耕田にて、動植物と環境調査、観察の実施(観察図の作成、見直し)、市民参加型イベント「水辺フォーラム」春の自然観察会・蛍の観察会・夏の自然観察会、ビオトープ整備(間伐材を利用した橋の設置や水位調節等を行います。
この希少地域のビオトープの刈払い整備や希少種を安全に安心して多くの方々が観察できるようにすることで、踏付被害防止、環境保全意識の高揚、里山(森林)とのふれあい、周辺域の森林整備を行いながら、地域に広く里山の重要性を実感していただき「地域の自然は地域で守っていこう」という意識の醸成につなげます。
また、里山の整備及び水辺空間(ビオトープ)の整備を地域ぐるみで取り組むことによって、地域の活性化につなげ、貴重な生物を後世に残すために長期ビジョンで取り組むことで、「生物生命の営み=人間生命の営み」として捉えられる様になるための、地域づくりと環境教育の普及を図ります。
それぞれの時点で観察データを蓄積させることにより、貴重な動植物の生息・自生状況を把握し、森づくりの成果を明確に提示します。
一言アピール
活動時期
5月~9月 ●ビオトープ調査
・動植物と環境調査、観察の実施(観察図の作成、見直し)
・ビオトープ研修会(水辺環境の現状確認など)
・ビオトープ整備(間伐材を利用した橋の設置や水位調節等)
5月 市民参加型イベント第1弾「水辺フォーラム」春の自然観察会
・イベントの中やその前後にもビオトープの整備を実施する
6月 市民参加型イベント第2弾「水辺フォーラム」蛍の観察会
・イベントの中やその前後にもビオトープの整備を実施する
7月 市民参加型イベント第3弾「水辺フォーラム」夏の自然観察会
・イベントの中やその前後にもビオトープの整備を実施する
対象となる希少生物種
動物:ゲンジボタル、ツクツクホウシ、ショウジョウトンボ、ハッチョウトンボ、メダカ他
植物:イチョウウキゴケ(国ランク絶滅危惧I類 CR+EN)、マツモ(県ランク準絶滅危惧NT)、トチカガミ、ヤマシャクヤク、アサザ他
実施団体プロフィール
遊学の森案内人会
【設立の目的】
本会は、「遊学の森」の活用を支援する「森の案内人」の資質の向上、会員相互の研鑽と親睦を図ることを目的とする。
【概要】
環境教育に根ざした活動(森林案内・木工クラフト)に必要な調査、プログラム開発。
①開園期間中の常設プログラム(森林案内・木工クラフト・食の体験・記念植樹・スノートレッキング)における案内活動。
②「遊学の森」で開催される「主催プログラム」等各種行事の企画・運営。案内人会による自主事業の開催。

特定非営利活動法人 山形の公益活動を応援する会・アミル
山形市市民活動支援センター内
023-647-2261