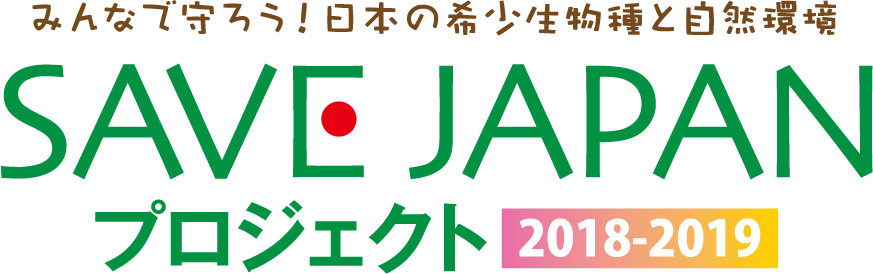シンポジウム「生物の視点からの環境・地域づくり~SDGs目標15を実現するために~」
2019年03月09日(土)実施

レポート
SAVEJAPANプロジェクトにて2014年から現在まで「いきものが住みやすい環境づくり」の実践報告と2030年に向けてSDGs(持続可能な開発目標)が進められる中で、これからの私たちの暮らし、地域づくりにつなげていくためのアイディアなど一緒に検討しました。
当日のスケジュール
13:00~ SAVEJAPANについて
13:10~ これまでの取組み報告
・ブッポウソウの保護・観察(活動と成果)
・ウスイロヒョウモンモドキの保護・観察(活動と成果)
・旭川かいぼり調査(活動と成果)
13:30~ 参考事例報告
・蒜山高原のサクラソウの保護活動
・ダルマガエルの保護・活用
14:45~ シンポジウム
・テーマ:生物多様性の保全と利用~いかに地域づくりにつなげていくか~
13:10~ これまでの取組み報告
・ブッポウソウの保護・観察(活動と成果)
・ウスイロヒョウモンモドキの保護・観察(活動と成果)
・旭川かいぼり調査(活動と成果)
13:30~ 参考事例報告
・蒜山高原のサクラソウの保護活動
・ダルマガエルの保護・活用
14:45~ シンポジウム
・テーマ:生物多様性の保全と利用~いかに地域づくりにつなげていくか~
実施内容
開会後、これまでの取組み報告として各分野の専門家より報告がありました。
まずはブッポウソウの保護・観察(活動と成果)として黒田聖子氏(ノートルダム清心学園教諭)より研究に至る経緯の紹介とブッポウソウの現状の説明があり、現在も全国的に減少傾向のままで、巣箱や餌、仲間が生息可能な里山環境が必要とお話しいただきました。

続いて、ウスイロヒョウモンモドキの保護・観察(活動と成果)から田井義明氏(新見市土橋地区振興会会長)より保護地域である新見市土橋の紹介があり、ウスイロヒョウモンモドキの生息地は全国で1か所に減少しているが、地元住民の協力を得て保護活動を続けており、新しい生息地をつくる活動もお話しいただきました。
旭川かいぼり調査では、齋藤達昭氏(岡山理科大学理学部准教授)より、当初は300人程度の参加だったが去年は600人まで増え、通算で33種の魚種が確認されており、河川に対する関心の向上が地域活性化にも繋がっているとお話しいただきました。
参考事例報告では蒜山高原のサクラソウの保護活動から、片岡博行氏(重井薬用植物園)、ダルマガエルの保護・活用を、友延栄一氏より説明いただき、それぞれの保護活動の内容と課題をお話いただきました。
片岡博行氏からの蒜山高原のサクラソウの保護活動発表

シンポジウムでは生物の保護活動をいかに地域で続けていくかを実際に活動している方より工夫している点や続けていくための課題など意見交換を行いました。

このイベントで得られたこと
SAVEJAPANプロジェクトを通じて、参加者は自然と生き物の暮らしのつながり、自然を守ることの価値を知ることができました。
また今回のシンポジウムではこれまでのSAVEJAPANプロジェクトに関わってきた方も参加いただくことにより、情報交換だけでなくつながりのきっかけや相互理解が深まりました。
また今回のシンポジウムではこれまでのSAVEJAPANプロジェクトに関わってきた方も参加いただくことにより、情報交換だけでなくつながりのきっかけや相互理解が深まりました。
参加者の声
- 希少生物の保全だけを考えても環境問題の解決につながるわけではない。様々な要素が複雑に関わり合っていることがわかった。
- 自分自身SAVEJAPANのイベントをきっかけとして環境について考えるようになった。もっとたくさんの人に興味を持ってもらうことが重要だと思う。
- 知っている人を対象に話をしても広がらない。専門家以外の人たちにもわかりやすい言葉で発信することを心がけたい。
イベント実施結果
- 参加者数
- 30名
- 実施してよかった点
- ・岡山県で生物を保護する団体の横のつながりと相互理解が深まりました。
・生物と人と地域との関わりが重要だと共有できました。地域の生活者視点での魅力づくりや次世代を担う若い世代に向けての楽しい体験を通した教育が必要だと感じました。 - 実施して苦労した点
- ・広報活動が遅かったため、講師との連携が不十分な結果となりました。
- 特に寄付が活きたと感じた点
- ・専門家、過去にSAVEJAPANプロジェクトに参加していた団体など、多くの関係者に登壇していただくことができました。
・アクセスのよい公共施設で開催することができ、遠方からの参加者が多く見られました。
- 主催・共催
- 一般社団法人高梁川流域学校
特定非営利活動法人岡山NPOセンター - 協力・後援等
- 認定特定非営利活動法人日本NPOセンター
- 協賛
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社