
越前海岸石づみアドベンチャー2025 完結編!

レポート
今年4月に手づくりした越前海岸にある水仙畑の「石づみ」を拡張し、より頑丈な「Eco-DRR」の“とりで”を完成させる完結編!
雨の中、みんなが一丸となって積み上げた石づみの体験は、達成感あふれる内容となりました!
当日のスケジュール
7:30 受付開始(鯖江)
7:45 バス出発~
8:45 現地到着(現地集合)
9:00 開会式
~損保ジャパンご挨拶
~重要文化的景観の話
~生きものの話
9:20 畑での生きものさがし
~石づみチャレンジ
11:30 移動~閉会式~アンケート
12:20 バス出発(現地解散)
13:20 鯖江着~解散
実施内容
4月のイベントからほぼ1ヶ月。
今年の「石づみ」体験は今回が最後となります。
曇り空の下、前回同様、無事に完成させることができるでしょうか?
 ▲さばえNPOセンターからバスで出発▲
▲さばえNPOセンターからバスで出発▲
こりゃ降りそうだな… ▲田植えも終わった田んぼを見ながら居倉(いくら)の水仙畑を目指します▲
▲田植えも終わった田んぼを見ながら居倉(いくら)の水仙畑を目指します▲ ▲漁港も見えて目的地はすぐそこ▲
▲漁港も見えて目的地はすぐそこ▲
1時間もかからずにフィールド近くの駐車場に到着です。
気がつけば、ボツリボツリと雨粒が…
参加者の皆さんも、カッパやポンチョ、レインコートで準備万端!
じゃあ、そろそろ開会式を始めましょう。
 ▲男の人なので「海女」じゃなく「海士」と書くとか…▲
▲男の人なので「海女」じゃなく「海士」と書くとか…▲
そういえば4月に集落の方にいただいたワカメ、絶品でした~☆ ▲駐車場横の建物には巣で休むツバメの姿も▲
▲駐車場横の建物には巣で休むツバメの姿も▲
白・黒・赤の組み合わせって美しい!
今日の体験イベントには、損保ジャパン福井支店の方々もお越しになっています。
参加者のご家族を前に、支店長さんから親しみやすい雰囲気でご挨拶いただきました。
続いて、講師の先生やスタッフからも、短めにそれぞれの“持ち場”のお話が。
活動について知識が増えて「頭の準備」ができたところで、さっそく水仙畑へと向かいましょう☆
 ▲損保ジャパン福井支店長さまのご挨拶▲
▲損保ジャパン福井支店長さまのご挨拶▲
去年はシンポジウムでしたが、今年は野外体験にご参加です☆
 ▲プログラム全体に目配りする(一社)環境文化研究所の田中さん▲
▲プログラム全体に目配りする(一社)環境文化研究所の田中さん▲
 ▲福井市立郷土歴史博物館の藤川さん▲
▲福井市立郷土歴史博物館の藤川さん▲
重要文化的景観「越前海岸の水仙畑」についてのお話
 ▲生きもののお話をしてくれた、さばえNPOサポートの久保田さん▲
▲生きもののお話をしてくれた、さばえNPOサポートの久保田さん▲
 ▲今年のSAVE JAPAN プロジェクトで作成した「越前海岸たんけんマップ」▲
▲今年のSAVE JAPAN プロジェクトで作成した「越前海岸たんけんマップ」▲
生きものもたくさん載ってるよ
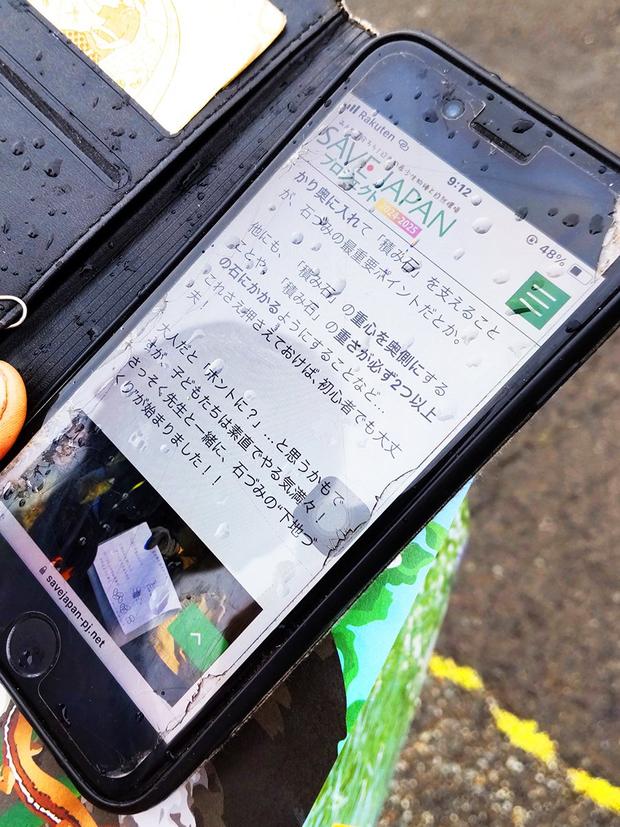 ▲「たんけんマップ」と一緒にもらった二次元コードを読み込むと…▲
▲「たんけんマップ」と一緒にもらった二次元コードを読み込むと…▲
SAVE JAPAN プロジェクト公式サイトの「レポート」も読めるよ
「あっ、これって!?」
今日の舞台となる水仙畑を目の前に、川沿いのコンクリートの道で何かを見つけた様子。
そこにはヘビの脱皮した皮が長々と横たわっていました。
1メートル以上はあろうかという大物の痕跡に子どもたちもざわめきます。
「それ、昔から“金運のお守り”とかも言われてるよね。」
スタッフの話に、ちぎれた皮を持って帰った子もいた様子。
自然と生きものと人間って、大昔から文化的にも深く繋がりあっていたんだなぁ。
さぁ、みんな畑に上がったら、まずは「生きものさがし」からスタートしよう!
 ▲下から見上げた「本日の活動場所(水仙畑)」▲
▲下から見上げた「本日の活動場所(水仙畑)」▲
崩れてるとこも多いけど
段段の「壁」のかなりの部分は「石づみ」でできてたんだよ
4月と同じように、「石づみ」体験の場所からは少し上のフィールドで生きものさがし。
雨の中でも子どもたちの好奇心は全開です。
家族で、友だち同士で、スタッフと…色々な生きものたちと出会うことができました☆
 ▲地面にはイノシシの足跡も!▲
▲地面にはイノシシの足跡も!▲
この冬は、水仙畑も荒らされて大変だったんだ
 ▲4月に続いて大物のクビキリギスをゲーット!▲
▲4月に続いて大物のクビキリギスをゲーット!▲
今回は緑色の子だねぇ
 ▲中にいたのはゲジくんでした▲
▲中にいたのはゲジくんでした▲
嫌われがちだけどダニとか食べてくれる「益虫」なんだって
 ▲虫かごの端っこにしがみついてた10mm弱くらいの甲虫くん▲
▲虫かごの端っこにしがみついてた10mm弱くらいの甲虫くん▲
もしかすると…モモブトカミキリモドキ(メス)…かな?
たくさんの生きものたちを見つけてふれ合った時間も終了。
下の段まで下りてきて、ここからは今日のメインイベント「石づみ」の始まりです。
世界を股にかけて「石づみ」を実戦している金子先生から、石づみの「コツ」をわかりやすく教えてもらいました。
・「積み石」は、どちらが「おもて」かを見極める
・ひとつの「積み石」は、必ず2つ以上の「積み石」で支える
・「積み石」の奥に、小さな「ぐり石」をたくさん詰め込むことで「石づみ」は強くなる!
あとは、怪我や事故のないように気をつければ、子どもたちにも「石づみ」づくりは全然可能なんです☆
ではでは、まずは材料となる「石」の調達からスタートして、本格的な「石づみ」を完成させていきましょう!
 ▲4月に完成させた「石づみ」の上でコツを教えてくれる金子先生▲
▲4月に完成させた「石づみ」の上でコツを教えてくれる金子先生▲
▲おっと! 石の間にサワガニ発見!▲
ホントに人の作った「石づみ」が生きものたちの「住処」になってるんだ
 ▲「石リレー」は想定以上の大盛り上がり!▲
▲「石リレー」は想定以上の大盛り上がり!▲
モチベーションもアがってきたー☆
材料(石)集めが一段落したところで、次はなんと「石づみ」崩し!
えっ!?
せっかく積んであるのに、どうして?
でも、一度古い「石づみ」を全部取り除いて“いちから積み直す”ことで、より強い「石づみ」が出来上がるんだ。
文字どおり「スクラップ&ビルド」。
これで100年単位で命を守れる「石づみ」になるのなら、そうしなきゃ!
 ▲先月完成させた「石づみ」の左の壁が今日の現場▲
▲先月完成させた「石づみ」の左の壁が今日の現場▲
まずは「崩し」て土が見えるようにするからね
 ▲みごとに崩れた石の壁(手前右側)▲
▲みごとに崩れた石の壁(手前右側)▲
この「石」が、また新しい「石づみ」に生まれ変わる!
そこにある材料を再利用できるのも環境負荷の少ない理由なんだね
 ▲むきだしになった土の壁▲
▲むきだしになった土の壁▲
これが新しい「石づみ」のカンバスに
これでやっと準備完了。
石を置き始める前に、恒例の「積み石の『おもて』はどーこだ?」検定の時間へ。
子どもたちはスグに知識を吸収して、かなりの正確さで「おもて」を見極められるようになってきました。
よーし、ここまで来たら、後は実践あるのみ☆
 ▲それじゃあ、各自、思い思いの「石」を持って積んでいくよーっ!▲
▲それじゃあ、各自、思い思いの「石」を持って積んでいくよーっ!▲
家族同士もスタッフも一緒になっての共同作業。
いつも以上に滑らないように、落とさないように気をつけながら…
でも、雨の中でのこんな体験、めったにできるものじゃないかも!
心なしか、子どもたちの表情も生き生きしているように感じられます。
 ▲今回も2ヶ所の「現場」で並行して進めていきました▲
▲今回も2ヶ所の「現場」で並行して進めていきました▲
(奥と手前)
 ▲時折り土の中から出没するサワガニに大興奮▲
▲時折り土の中から出没するサワガニに大興奮▲
こんなトコロにいるとは思わないよね
 ▲上から見るとわかりやすい「積み石」と「ぐり石」の関係▲
▲上から見るとわかりやすい「積み石」と「ぐり石」の関係▲
「ぐり石」の充実度が「石づみ」の強さのヒミツ!
 ▲地面近くを補強するための「土」も重要な素材▲
▲地面近くを補強するための「土」も重要な素材▲
たのもしいなぁ
 ▲そろそろ完成も見えて来た▲
▲そろそろ完成も見えて来た▲
ひとつひとの「石」が、みんなの「仕事」の証だね
そして、ほぼ1時間弱で立派に完成した2つの「石づみ」。
雨の中だからこその大変さもあったけど、きっとその分、みんなの思い出にもなってくれると嬉しいな。
…自分もなんだか、正直ちょっと感動しちゃいました。
さぁ、少し雨脚も強くなる中、駐車場へと戻ります。
そして閉会式でのふりかえりとアンケート…
無事プログラムが完了できたことに感謝しつつ、家路へと向かいましょう。
このイベントで得られたこと
・4月と同様、一見難しそうな「石づみ」も、コツがわかれば自分たちのチカラでもできることが体感できた。
また、それが100年単位で「人の生活」「生きものたちの命」「環境」「防災や減災」に役立つ(Eco-DRR)ことも感じることができた。
・4月のイベントと同じフィールドで「生きものさがし」をすることで、季節が少し違うだけでも見られる生きものに変化があることを知ることができた。
また、石づみの奥の「土の中」からサワガニを発見するなど、思いもしない生態を学ぶこどができた。
・親子、家族、スタッフ、損保ジャパンのメンバーさんとも一緒に立派な構築物を完成させたことで、深い達成感と一体感を共有できた。
参加者の声
- みんなで石リレーが楽しかったし、みんなで(スタッフ)石づみができて楽しかったです。カニがりくにもすんでいてびっくりしたし石づみつくり方がしれてうれしかったです。(3年生)
- 今まで石づみたいけんに行ったけど、きょうだけ、よくわかったり、たのしかったり、レインボーの虫をつかまえて、すごく楽しかった。ありがとうございました。(5年生)
- 石づみののせかたとか、やりかたをしれてうれしかったです。(4年生)
- 天候が残念ではありましたが、子どもが一生懸命がんばっている姿が見られてほほえましかったです。(30代)
- 昔からの日本の知恵を知り、興味深かった。これからの日本を作っていく子供たちにとって、良い学び、経験になったと思います。ありがとうございました。
イベント実施結果
- 参加者数
- 36(大人16名 / 子ども20名)
- アンケート回答数
- 32(大人14名 / 子ども18名)
- 参加者満足度
- 79%
- 実施してよかった点
・雨天だったことも含め、良い意味で「非日常の体験」が得られたと思う。
参加者もスタッフも一緒に、100年単位で環境と地域に資する構築物を完成させられたことは、一種の「成功体験」として子どもたちの記憶に残ってくれることを期待している。
・損保ジャパン福井支店長様と社員の方にも、様々なサポートをしていただいた。
ご挨拶ももちろんだが、精力的に石運びをされたり、参加者の皆さんとのコミュニケーションとったりと、スタッフも含めた“一体感”を醸成していただいたと思う。
そのおかげで、多様な立場のメンバーで共同作業することの醍醐味を感じられた時間となった。- 実施して苦労した点
・雨の中での活動となり、安全面を含めた当日の運営で苦労した。
基本、傘をさしての活動はムリなので、参加者の皆さんには「カッパ」「ポンチョ」等の用意をお願いしていたが、しっかりと対応していただいてありがたかった。
結果的には、雨の中での活動を経験する機会が少ないこともあり、記憶にも強く残ってくれるかもしれない。
実際、子どもたちの多くは、雨の中であることをほぼ気にしていないか、逆に楽しんでいたようにも感じられた。
ただし、帰宅後の健康管理や洗濯等の負担を考えると、参加者のご家庭のサポートなくしては無事に遂行できないプロジェクトであることも痛感させられた。
あと、広報用の写真撮影も、雨の中では一眼レフよりスマホの方が有利な点も多く、多くのスタッフの撮影データを提供してもらえて助かった。
・石づみの材料となる「積み石」「ぐり石」の確保&準備に手間がかかった。
ある程度の量をエリアのあちこちから調達して事前に確保をしていたものの、実際に積んでみると全部が使えるとも限らないのが正直なところ。
逆に、石づみから「崩れた石」を材料にできることも手づくり石づみの環境負荷が低いメリットでもあるので、材料不足の部分は、その方法で調達し、新しい石づみに生まれ変わらせることができた。
「あるもので」「できる方法で」手づくりすること=持続可能なスキームということを、ある意味体現したような結果にもなった。- 特に寄付が活きたと感じた点
・移動バスのチャーターが無理なくできた。
・各専門家の講師をお呼びして、貴重な体験を指導してもらえた。
・虫採り網やカゴなどの備品を用意することができた。
・告知のチラシを必要な数と質で作成し、十分な形で配布することができた。
- 主催・共催
◆共催
認定特定非営利活動法人 さばえNPOサポート
一般社団法人 環境文化研究所
福井市立郷土歴史博物館
くにみクラゲ公民館- 協力・後援等
◆協力
認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター
◆後援
鯖江市教育委員会- 協賛
- 損害保険ジャパン株式会社








































