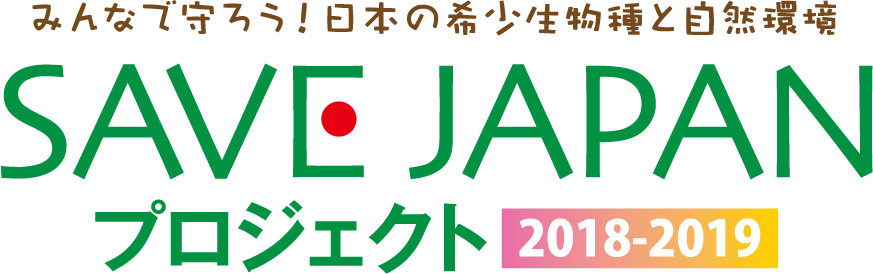アカミミガメ捕獲調査+外来生物勉強会
2019年05月19日(日)実施

レポート
前半は、ミシシッピアカミミガメの問題を切り口に、佐鳴湖や各地の淡水ガメ、外来種をめぐる現状を学びました。
後半は、実際にワナを回収して、カメの種類や雌雄、大きさなどを記録しました。その中には、イシガメとクサガメの雑種や、特定外来種のハナガメの雑種がいて、今後どう扱っていくべきか考えさせられました。
後半は、実際にワナを回収して、カメの種類や雌雄、大きさなどを記録しました。その中には、イシガメとクサガメの雑種や、特定外来種のハナガメの雑種がいて、今後どう扱っていくべきか考えさせられました。
当日のスケジュール
13:00~14:50 外来種勉強会
「佐鳴湖の淡水ガメ」小林芽里(昆虫食倶楽部)
「アカミミガメ対策の最前線」片岡友美さん(認定NPO法人生態工房)
「中池見湿地のカメのお話」西堀智子さん(和亀保護の会)
「イシガメとクサガメの交雑問題」三根佳奈子さん(株式会社自然回復)
みんなでディスカッション
15:00~17:00 アカミミガメ捕獲調査(ワナの回収とカメの計測・記録)
「佐鳴湖の淡水ガメ」小林芽里(昆虫食倶楽部)
「アカミミガメ対策の最前線」片岡友美さん(認定NPO法人生態工房)
「中池見湿地のカメのお話」西堀智子さん(和亀保護の会)
「イシガメとクサガメの交雑問題」三根佳奈子さん(株式会社自然回復)
みんなでディスカッション
15:00~17:00 アカミミガメ捕獲調査(ワナの回収とカメの計測・記録)
実施内容
外来種勉強会では、まず佐鳴湖の2017年、2018年の調査結果から。
2017年は9割がミシシッピアカミミガメでしたが、2018年は調査地点を増やしたこともあり、アカミミは6割で、クサガメが3割、残りがイシガメ、スッポン、ハナガメの雑種などでした。アカミミが獲れる率は減りましたが、特定外来生物のハナガメの雑種が見つかったり、イシガメとクサガメの雑種や、棄てられた疑いのあるイシガメなど、様々な問題が見えてきました。
生態工房の片岡さんは、東京でアカミミガメに関して駆除の手法や体制を提案し、飼育個体を捨てさせない普及啓発や終生飼養の徹底もはかり、野外個体を減らす取り組みを20年余り行っています。また、外来生物法改訂の環境省の動向、生物多様性条約の愛知目標での外来種対策の位置づけなど、カメをめぐる施策についても説明がありました。
和亀保護の会の西堀さんからは、北陸のラムサール条約登録の中池見湿地で、イシガメ×クサガメの雑種が37%もいた!という問題。これまで日本のカメとされていたクサガメは、実は数百年前に中国から来た外来のカメとわかり、この雑種のカメが在来種のカメと子どもを作ると、絶滅危惧種のイシガメがさらに減ってしまう。その対策として、説明会や意見交換会でクサガメの扱いを考えたり、クサガメ収容池や里親制度を作ったり、DNA分析と照合して雑種の見分け方の判定基準を作成したというお話でした。
自然回復の三根さんからは、イシガメは日本で、クサガメは中国・朝鮮で進化させた独自の遺伝子を持っているけれど、雑種をつくるとその遺伝子が失われてしまうこと。イシガメは世界でも日本にしかいない固有種で、その独自の遺伝子が失われることは日本の生物多様性にとって大きな損失になる。雑種が増えていくと、約30年後には純粋な種が失われ絶滅してしまう危険性が指摘されているというお話でした。

ディスカッションでは、アライグマがイシガメの天敵となってカメが激減してしまった例や、ヌートリアの生息域がカメと競合する話、日本でカワウソやカピバラを見た!という話の正体はほぼヌートリアで、佐鳴湖でも2年前から生息が確認されており、見つけたら浜松市環境政策課に通報してほしい、という話もありました。イシガメは河川改修の影響だけでなく、販売業者の乱獲も酷いという話や、クサガメは中国では食用で減ってしまったという話に、思わずどよめきも。
生物はもともと移動分散したり、雑種を作ったり、何万年~何億年の時間をかけた進化の過程を経て現在の生物多様性を形作ってきましたが、人間が生物本来の移動距離を越えて生物をあちこちへ運ぶことで、様々な悪影響を起こしているのが外来種問題です。
人とモノの移動が激しい時代ですが、防げるものはできるだけ手をうち、よりよい生物多様性を次の世代に手渡したいものです。

後半は、佐鳴湖の北岸で3グループに分かれてワナを回収。21か所のワナからアカミミガメ、クサガメ、イシガメなど計105匹の「大漁」!カメのスペシャリストの手ほどきで、雌雄の見分け方や計測の仕方など、ばっちり教えていただきました。
その中には、クサガメとイシガメ両方の特徴を持つ明らかな「雑種」や、特定外来生物に指定されているハナガメとクサガメの雑種も見つかりました。


今回は初めてクサガメがアカミミガメとほぼ同数になり、クサガメの扱いをどうしよう???となりましたが、改めて議論を深めていくことにして、今回は放流して終了しました。
2017年は9割がミシシッピアカミミガメでしたが、2018年は調査地点を増やしたこともあり、アカミミは6割で、クサガメが3割、残りがイシガメ、スッポン、ハナガメの雑種などでした。アカミミが獲れる率は減りましたが、特定外来生物のハナガメの雑種が見つかったり、イシガメとクサガメの雑種や、棄てられた疑いのあるイシガメなど、様々な問題が見えてきました。
生態工房の片岡さんは、東京でアカミミガメに関して駆除の手法や体制を提案し、飼育個体を捨てさせない普及啓発や終生飼養の徹底もはかり、野外個体を減らす取り組みを20年余り行っています。また、外来生物法改訂の環境省の動向、生物多様性条約の愛知目標での外来種対策の位置づけなど、カメをめぐる施策についても説明がありました。
和亀保護の会の西堀さんからは、北陸のラムサール条約登録の中池見湿地で、イシガメ×クサガメの雑種が37%もいた!という問題。これまで日本のカメとされていたクサガメは、実は数百年前に中国から来た外来のカメとわかり、この雑種のカメが在来種のカメと子どもを作ると、絶滅危惧種のイシガメがさらに減ってしまう。その対策として、説明会や意見交換会でクサガメの扱いを考えたり、クサガメ収容池や里親制度を作ったり、DNA分析と照合して雑種の見分け方の判定基準を作成したというお話でした。
自然回復の三根さんからは、イシガメは日本で、クサガメは中国・朝鮮で進化させた独自の遺伝子を持っているけれど、雑種をつくるとその遺伝子が失われてしまうこと。イシガメは世界でも日本にしかいない固有種で、その独自の遺伝子が失われることは日本の生物多様性にとって大きな損失になる。雑種が増えていくと、約30年後には純粋な種が失われ絶滅してしまう危険性が指摘されているというお話でした。

ディスカッションでは、アライグマがイシガメの天敵となってカメが激減してしまった例や、ヌートリアの生息域がカメと競合する話、日本でカワウソやカピバラを見た!という話の正体はほぼヌートリアで、佐鳴湖でも2年前から生息が確認されており、見つけたら浜松市環境政策課に通報してほしい、という話もありました。イシガメは河川改修の影響だけでなく、販売業者の乱獲も酷いという話や、クサガメは中国では食用で減ってしまったという話に、思わずどよめきも。
生物はもともと移動分散したり、雑種を作ったり、何万年~何億年の時間をかけた進化の過程を経て現在の生物多様性を形作ってきましたが、人間が生物本来の移動距離を越えて生物をあちこちへ運ぶことで、様々な悪影響を起こしているのが外来種問題です。
人とモノの移動が激しい時代ですが、防げるものはできるだけ手をうち、よりよい生物多様性を次の世代に手渡したいものです。

後半は、佐鳴湖の北岸で3グループに分かれてワナを回収。21か所のワナからアカミミガメ、クサガメ、イシガメなど計105匹の「大漁」!カメのスペシャリストの手ほどきで、雌雄の見分け方や計測の仕方など、ばっちり教えていただきました。
その中には、クサガメとイシガメ両方の特徴を持つ明らかな「雑種」や、特定外来生物に指定されているハナガメとクサガメの雑種も見つかりました。


今回は初めてクサガメがアカミミガメとほぼ同数になり、クサガメの扱いをどうしよう???となりましたが、改めて議論を深めていくことにして、今回は放流して終了しました。
ハナガメ×クサガメの雑種
クサガメ×イシガメの雑種
昆虫食倶楽部のレポート「SAVEJAPANプロジェクト1回目、2回目開催しました。」
このイベントで得られたこと
・各地のカメの現状や取り組みを知らせることができた。
・実際にカメを見て、雑種がいる状況を見せることができた。
・カメのスペシャリストに見ていただき、種類や雌雄の識別ポイントを学ぶことができた。
・実際にカメを見て、雑種がいる状況を見せることができた。
・カメのスペシャリストに見ていただき、種類や雌雄の識別ポイントを学ぶことができた。
参加者の声
- 実際にカメを捕獲して計測等ができたので、現実に起きていることを肌身を持って実感でき、とても関心が向上しました。(40代女性)
- 講義はいずれも興味深かった。調査の雌雄判別でも講師陣のヒントがないとわからないものあり、3人の知見はすばらしかった。後半は見守るだけの人もおり、特定の人に計測が偏った。チームリーダーの丁寧な声掛けと誘導が必要。(50代女性)
- 日本の固有種と外来種を見れたから。(10代、男性)
- 外来種問題の現状を知る事は出来た。アカミミガメ殺処分ありきの活動には疑問。人間のエゴによる問題が、殺して解決になるのか?恐怖心も同時に感じ、活動のあり方に工夫が必要だと思われる。(女性)
- 新たな知識が増え、しかも実技を通して理解できたから。(50代男性)
イベント実施結果
- 参加者数
- 22名(大人17名、子ども5名)+スタッフ5名+ゲスト3名
- アンケート回答数
- 17名(大人13名、子ども4名)
- 参加者満足度
- 77%
- 実施してよかった点
- ・参加者には学校の先生が多く、今後の連携や普及啓発に期待ができそう。
・座学と実践が結びつけられた。
・中学生や大学生の若い世代の参加があった。 - 実施して苦労した点
- ・調査器具の扱いや、計測方法の説明がなかなか全員に行き渡らない。説明に工夫が必要。
・カメの捕獲数が予想以上に多くて、記録に時間がかかった。
・今回は天気がよかったが、お天気に左右されないか心配だった。 - 特に寄付が活きたと感じた点
- ・遠くからカメの専門家を招くことができた。
・調査が3年目になり、調査機器や備品、資料などを補充、新調することができた。
- 主催・共催
- 主催:昆虫食倶楽部
共催:認定NPO法人 浜松NPOネットワークセンター - 協力・後援等
- 協力:認定NPO法人 日本NPOセンター
- 協賛
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社