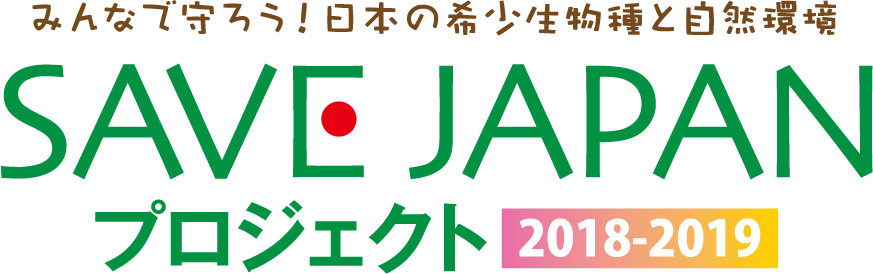アカミミガメ捕獲調査+解剖してみよう

レポート
佐鳴湖に住んでいるカメの種類とその割合を、捕獲調査をする事で確認。生息環境を実際に見て、生態を知る事が出来ました。
次に、ミシシッピアカミミガメを解剖し、人間とカメの体のつくりを比較しました。外来種の問題や、ミシシッピアカミミガメの生態と体のつくりについての理解を深める機会となりました。
当日のスケジュール
9:00〜11:30 カメわなの回収、記録
終わり次第、各自昼食・移動
13:00〜16:00 解剖実習
解剖指導:西岡愛香さん(聖隷クリストファー中・高等学校)
ミニ講座
「アカミミガメ駆除はなぜ必要か」三根佳奈子さん(自然回復)
実施内容
まずは、佐鳴湖の北岸に集合して、3班に分かれて前日に仕掛けたワナ(カニかご)計20個を回収しました。
2日前は大雨が降ったこと、満潮時で水がひたひただったことが影響したのか、前週の調査より少ない56匹のカメが捕獲されました。50㎝級の大きなコイが3匹入ったワナもありました!

ミシシッピアカミミガメ、クサガメ、イシガメ、スッポン、それぞれ特徴や雌雄の見分け方を詳しく説明。
背中の甲羅の長さ、お腹の甲羅の長さをノギスで計測して記録しました。

今回はアカミミガメ、クサガメと外来のカメが大半を占め、クサガメがかなり多かったのですが、専門家の西堀さんいわく「アカミミは警戒心が高く、クサガメの方がワナに入りやすい傾向がある。ワナに入らないからといって、アカミミがいないわけではない」とのこと。むむー。

午後は、静岡大学に移動して、生物実験棟へ。
生物が専門の西岡愛香さんが実験の手ほどきと解説をしました。
まず、腹甲をノコギリとノミとカッターで外します。
写真は甲羅をのこぎりで切る昆虫食倶楽部の夏目代表。
カメは両生類、爬虫類、どっち?
カメの臓器と人間の臓器の相違点は?
オス、メスの生殖器官はどこ?
卵は何個ぐらいある? 卵は一度に何個、どれくらいの間隔で生む?
どんな体位で交尾する?
その後3~4人で1班になり、眼科用解剖ばさみで薄い膜を切って、肝臓・心臓・消化器官・気管・肺・卵巣・精巣などをを切り離していきました。
人間の臓器の立体紙模型と見比べながら、カメの臓器を確認。
気管にストローを挿し、空気を送って肺を膨らませる実験もしました

「これは脾臓かな?脾臓って何する臓器?」「副腎はどこ?」「甲状腺は?」という難しい質問も出て、参加者の探究心に驚く場面も。

今回、脂肪肝や卵殻の癒着した病変個体もあり、正常個体の臓器と比較する事が出来ました。
健康な赤黒いレバーとは、色もやわらかさもかなり違います。

最後に、カメの捕獲・研究をしている三根さんから「アカミミガメ駆除はなぜ必要か」と題して、日本の淡水カメの現状、イシガメが減った原因、殺処分以外の選択肢についてお話しいただきました。
年間数百、数千匹を全て収容して飼うことは難しくても、今回の解剖のように有効に活用する方法もあります。解剖後は、カメの内臓と甲羅は肥料化しています。更に昆虫食倶楽部では、カメの甲羅を楽器にしたり、肉を食用にしています。
人の都合で増えてしまった外来種のカメに罪はありません。
駆除したカメ達を使って、何かの役に立つ方法を考えたいと思っています。
活用方法のアイデアを皆さんから出していただけると幸いです。
昆虫食倶楽部のレポート「SAVEJAPANプロジェクト1回目、2回目開催しました。」
このイベントで得られたこと
・前回に続いて、カメの種類や雌雄の識別をしっかり学ぶことができた。
・調査と解剖を組み合わせたことで、カメの生態についてより深く学ぶことができた。
・最近は、小中高の授業では脊椎動物の解剖をやらないので、貴重な機会を提供できた。
・「解剖」という他の環境イベントにはないプログラムがあったことで、幅広い参加者を得ることができた。
参加者の声
- かめの解剖の体験ができて、とても満足です。実際に在来種に対する外来種の数の方が多く、捕獲できる現状が知れて、よい経験ができました。(30代男性)
- 普段飼っている身近なカメの体のつくりを知ることができて嬉しかった。カメの特性、生態などの知識もたくさん増えて、とても充実したイベントでした。常連の家族の方々、子どもたちのたくましさに驚きました。普段関わらない方々と話すこともできて、遠くから来てよかったです。次回も参加したいです。(20代男性)
- 生物の解剖をする機会が全くなく、初めて動物(カメ)をハサミで切りましたが、普段からこのようなイベントがあると、もっとご飯へのありがたみが増えるのになと思いました。初めてだらけで、とても楽しく学ぶことができました。(20代女性)
- カメの体の構造を少しずつ人と比べながら説明してもらったので良くわかった。体のつくりを知ることでカメの生態もわかり面白かった。ありがとうございました。(50代女性)
- 暇な時間を環境保全活動につなげようと思いました。(30代男性)
イベント実施結果
- 参加者数
- 29名(大人21名、子ども8名)
- アンケート回答数
- 26名(大人20名、子ども6名)
- 参加者満足度
- 90%
- 実施してよかった点
- ・佐鳴湖に生息する4種のカメを見せることができた。
・大学と協働することで生物実験室をお借りして、充実した施設環境で取り組むことができた。
・損保ジャパン日本興亜の浜松支店に広報協力していただいて、新たな参加者を得ることができた。
・主催者団体も、講師を迎えたことで解剖に関する知見や技術を増すことができた。 - 実施して苦労した点
- ・自然の状況は気まぐれなので、どんなカメがどれだけ獲れるか、全く予測できない点
- 特に寄付が活きたと感じた点
- ・消耗品である実験道具を補充することができた。
・遠くからカメの専門家を招くことができた。
- 主催・共催
- 主催:昆虫食倶楽部
共催:認定NPO法人 浜松NPOネットワークセンター
静岡大学アメニティ佐鳴湖プロジェクト
- 主催:昆虫食倶楽部
- 協力・後援等
- 協力:認定NPO法人 日本NPOセンター
- 協賛
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社