
しめっちカフェ 湿地の保全に地図情報を活用しよう 〜「湿地マップ」づくりで保全と防災〜
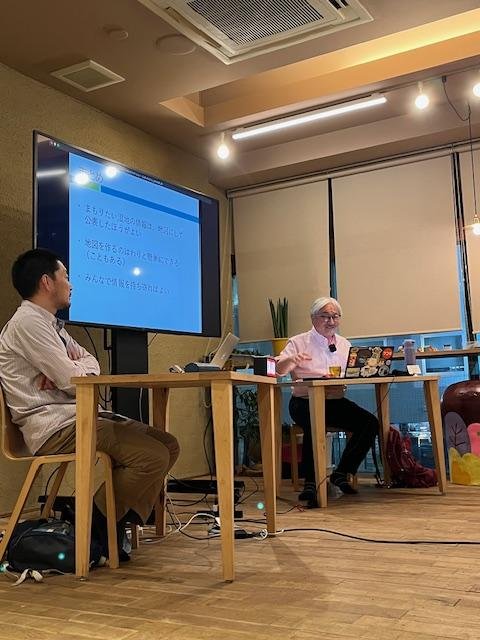
レポート
自然環境の評価・分析や計画策定など、広域的に検討できるGIS(地理情報システム)は広く活用されてきており、地理空間情報の可視化によって、傾向や関連性など様々な情報を一目で把握できるため、自然環境保全に有効なツールとなっている。
また、生きものアプリなどによって、生物多様性情報の収集・解析・可視化技術も進んでおり、自分たち含め個人が得た情報のMAP化や共有による情報活用の可能性も広がっている。そのような「地図情報」をどのように得て、自然環境の保全や防災減災にどう活用できるのか、現場の調査から計画まで関わってきている専門家に伺いました。
Guest Speaker
長谷川 理 NPO法人EnVision環境保全事務所
北海道大学大学院地球環境科学研究科博士課程修了・博士(地球環境科学)。学生時代からタンチョウを中心に希少鳥類の調査研究に従事。また、道内各地で野生動物に関するトークイベントや市民フォーラムなどの普及啓発活動を企画・開催。趣味は犬の散歩。
当日の内容は以下のyoutubeよりご覧いただくことができます
https://www.youtube.com/live/wH8MedgyzIo?si=cF7b84z9OjkXG31i
当日のスケジュール
・石狩川流域の湿地について
・地図情報を活用しよう
・湿地の保全に地図情報を活用できること、他の地図情報アプリの事例等紹介
実施内容
■最近の情報収集の方法
世の中のない情報、新しい情報(生き物の情報)などは研究者独自で情報収集していた。
<GISの活用について>
釧路湿原をはじめとする湿地の保全には、**GIS(地理情報システム)**の活用が不可欠である。GISとは、地理的な情報を地図上で可視化・分析する技術であり、自然環境のモニタリングや変化の追跡、保全計画の立案などに活用されている。
衛星データやドローンによる空撮画像、現地調査の結果などをGIS上で統合・管理することにより、以下のような利点があると説明されていた:
湿原の面積や土地利用の変化を経年的に比較できる
→ どこが乾燥化しているか、植生がどう変わったかを客観的に把握
再生事業や保全活動の成果を視覚的に評価
→ 植生の回復状況や水位の変化をGISで定量的に示せる
地域住民や行政との情報共有の手段
→ 地図上で「どこで何が行われているか」を示すことで、関係者との合意形成がしやすくなる
このイベントで得られたこと
・釧路湿原に棲むキタサンショウウオ(天然記念物)の生息地を例にあげて、希少生物種の分布情報が公開されていなかったため、いないものと扱われてしまった現状があった。
→実際にいる場所は公開しないほうがよいが、生息適地(いそうな環境、場所)を出すことが希少生物の保全を行う上で大事ということがわかった。
・政策への活用として
地理情報を条例、ガイドライン、行動計画/地理戦略、ゾーニングに使用することをおしえていただいた。
希少生物種の生息状況マップを作成し、生物の存在・利用状況・生息適地を把握することで、センシティビティマップとして開発等への影響を推測し、評価へつなげる。また、ゾーニング(対策の方針)策定へ進むということがわかった。
特に、ゾーニングに関しては、各自治体にて異なる。釧路湿原は、釧路市、釧路町、鶴居村、標茶村がかかわっているため、それぞれのガイドライン・条例にて使用しているということ。
参加者の声
- 実際のアプリを紹介いただいたことで、実際に試す上での敷居が低くなった
- 希少種生息域を公開しないことが釧路湿原の開発が止められなかったことを初めて知りました
- 防災減災より情報公開の話が中心だったように思う
- 湿地を知ったのは北海道に来てからでした。また、観光したこともないけれど(行ってみたい)、湿原は森みたいに失ってしまったら、元に戻すことは難しく労力もかかるのだろうなぁ〜のイメージだけで伺いましたので、素人だし用語は難しかったです。 しかし、初めてですが、お話しは興味深かった
- 印象に残ったのは、シマフクロウの生息地において、種の交雑が出来ていないと知ったこと。今後の取り組みを期待しています。 良かった点は、ひとつひとつの用語を丁寧に説明いただき、わかりやすかったこと。今後も楽しみにしています。
イベント実施結果
- 参加者数
- 13
- アンケート回答数
- 6
- 参加者満足度
- 75%
- 実施してよかった点
・様々な地図情報アプリがあり、実際に使用している方たちがおり、色々なことが共有できたこと。
・長谷川さんが経験されたリアルな内容を聴くことができた
・湿地や希少生物種保全・保護のためには色々な方法があることを知れたこと
- 実施して苦労した点
地図情報の作成により自然環境の保全に繋がることは伝えられたと思うが、防災・減災との関わりをうまく伝えられなかったのかもしれないと思った
- 特に寄付が活きたと感じた点
・現場で関わる長谷川さんの話を聴くことができたこと
- 主催・共催
主催:石狩川流域 湿地・水辺・海岸ネットワーク(しめっちネット)
共催:特定非営利活動法人北海道NPOサポートセンター
- 協力・後援等
協力:特定非営利活動法人日本NPOセンター
- 協賛
- 損害保険ジャパン株式会社


